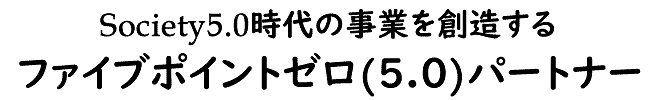目次
これまでの常識が変わる
満員電車や自動車で毎朝会社に向かうというのは当たり前の日常ですが、そうでなくなる日も近いかもしれません。
IT化が進んだ企業では、紙の資料がなくなり、契約手続きはオンライン化され、社内外のコミュニケーションツールは用途によって様々な組み合わせができるようになりました。

ただ、これまでの企業でのIT活用は、基本的に既存のビジネスモデルは変えることなく、IT活用はそのビジネスモデルの様々な部分の効率化を主な目的としていました。
IT活用に求める事の変化
最近では、既存の常識に捉われない、ITを中心に構築した新しいビジネスモデルが次々と誕生し、ITを補完的に活用してきたビジネスモデルを駆逐しています。

デジタル技術による創造的破壊
店舗での漫画や映画のレンタルサービスは、NetflixやU-NEXTなどのサブスクリプション型ビジネスになり、家や車や自転車はUberやAirbnbなどのシェアリングエコノミー型へと変化しています。
従来は各飲食店の従業員が行っていた出前サービスは、UberEatsなど街中配達員を共有するシェアリングデリバリー型となり、美味しい料理が提供できれば店舗すら必要がなくなっています。
シェアリングデリバリーサービスを例にとってみても、
- 飲食品を必要としている人
- 必要とされる飲食品を提供(調理)できる人
- 飲食品を必要としている人に配達できる人
それぞれに対して「商品検索」から「配達&決済」に至るまでの様々な情報交換をオンラインで即時に行えるようになったからこそ実現できているサービスです。
ITが浸透した社会でなければ、成立しなかったビジネスモデルと言えます。
金融サービスでは、フィンテック(FinTech)によるキャッシュレス化も進み、ネット銀行やネット証券は従来と比べて低価格でありながら、様々なサービスを提供してくれます。従来型の銀行や証券会社は店舗や多くの営業社員を抱えており、それらの維持は投資ではなくコストに変わりつつあります。
また、Amazonにより、書籍や雑貨などを安く、店舗ではなかなか見つからない製品でも当日に届けてくれるという便利なサービスが当たり前になり、書店やおもちゃ屋などの経営破綻の要因となっている事は周知の事実です。
衣類もネット販売は流行らないと言われていましたが、ZOZOなどテクノロジーの進化もあって活性化しています。
訪日中国人の多い 和歌山県では、中国大手のライドシェア企業「滴滴出行(DiDi)」とソフトバンクの合弁会社が、2020年1月からタクシー配車サービスを開始しており、「DiDi」アプリでタクシーを呼び、車両の特徴や接近情報の確認、決済まで行うことができます。
※2018年3月に和歌山市でスタートした中国シェアサイクル企業の「ofo」は約半年で撤退となってしまっていました。
デジタル社会への対応
ITが様々な部分にまで浸透した社会では、ITを中心とした新しいビジネスモデルを創造し進化を続けなければ生き残れません。ITの専門家である必要はありませんが、ITについて理解を深められない経営者は、企業の舵を取り稼ぎ続けることは難しくなるでしょう